私はインドネシアの日系企業で3年間勤務していました。駐在員の補佐が仕事で、駐在員とローカル社員(インドネシア人)間のコミュニケーションの橋渡し的な役割でした。インドネシアに留学経験のあった私はインドネシア語に不安はなく、入社時は「きっと楽しく働けるだろう」と、かなり楽観的に考えていたのですが、うまくいかずに思うように仕事が進まないことも多々ありました。その時に自分なりに学んだことを、お話してみたいと思います。
先ずは職場のローカル社員達と打ち解けよう

私はとにかく積極的にコミュニケーションを取ることを心がけました。
インドネシア人は親身で世話好きな人が多いので、同年代の女性従業員にはおすすめのTVや音楽、美容のこと、年配の女性には服のシミの落とし方や民間療法、男性には携帯電話の安い店や修理方法、アプリのダウンロードの仕方など、日常生活に関するアドバイスを求めたり、疑問に感じたことをどんどん聞いてみたりしました。
仕事以外の話でお互いを知る
休憩時間には同じものを一緒に食べたり、家族をとても大切にする彼らの子育てについての話を聞いたりと、仕事以外の時間にローカル社員との距離を縮め、彼らの文化や考え方を理解し、また私という人間に親近感をもってもらうことで、仕事の際の意思疎通もよりスムーズになったと思います。
笑顔は大切!でも笑顔だけじゃだめ!!

インドネシア人はとても人懐っこい人が多く、仕事の時でもニコニコしています。つい、私もつられて笑顔になってしまいます。しかし、仕事を指示した時に、笑顔で”OK!!”という返事が来るのでこちらも安心していたものの、実はこちらの意図がまったく伝わっていなかった… ということもよくありました。
具体的に伝えて、再確認する
笑顔でのやりとりは円滑なコミュニケーションにおいて重要ですが、それだけで終わらず、仕事をお願いする時はその仕事の目的とやり方を具体的に伝え、相手が理解しているかを再度確認して念を押すことが、正確に意思疎通して仕事を効率的に進めるためにも大事だと思いました。
褒めることで職場全体の雰囲気も変わる
その分、いい仕事をしてくれた時には大げさなくらいに「ありがとう~!本当に助かったよ!!」とお礼を言うようにしていました。褒められるとさらにやる気を持って取り組んでくれ、職場の雰囲気も良くなったと思います。
通訳以上の役割を

立場上、駐在員からの注意や批判等をローカル社員に伝えることも多かったのですが、皆プライドを持って仕事をしているので、20代の私が年上のベテラン社員達にどのようにそれを伝えればいいか、悩みました。「生意気だ」と反感を買い、素直に受け入れてもらえなかったこともあります。
それゆえ、伝える内容に拘わらず、特に年長のローカル社員には、敬称を忘れず、敬う気持ちをしっかり示すことを心がけました。
言葉の裏にあるお互いの文化を伝えよう
ただ会社の意向を訳してストレートな言葉で伝えるだけではなく、インドネシア人の文化ややり方に理解を示し、ローカル社員には日本人の考え方や求めることを、また日本人にはインドネシア人の考え方ややり方をそれぞれ伝え、ただの通訳だけではなく、より深く橋渡しをすることに心を砕きました。
お互いの違いにストレスを感じるのではなく楽しもう!

語学力さえあればやっていけるだろう、という気持ちで入社した私ですが、通訳業務にしても、言葉の裏にある考え方や文化を理解していないと、ただ言葉を伝達することしかできず、議論が進まない、いくら言葉ができても相手の文化や考え方を理解しないと、仕事が思うように進めらない、もちろん楽しく働くこともできない!ということに徐々に気付くようになりました。
外国人と一緒に楽しく仕事をするには、自分と相手の相違にストレスを感じるのではなく、それを受け入れて、おもしろがることが必要だと思います。

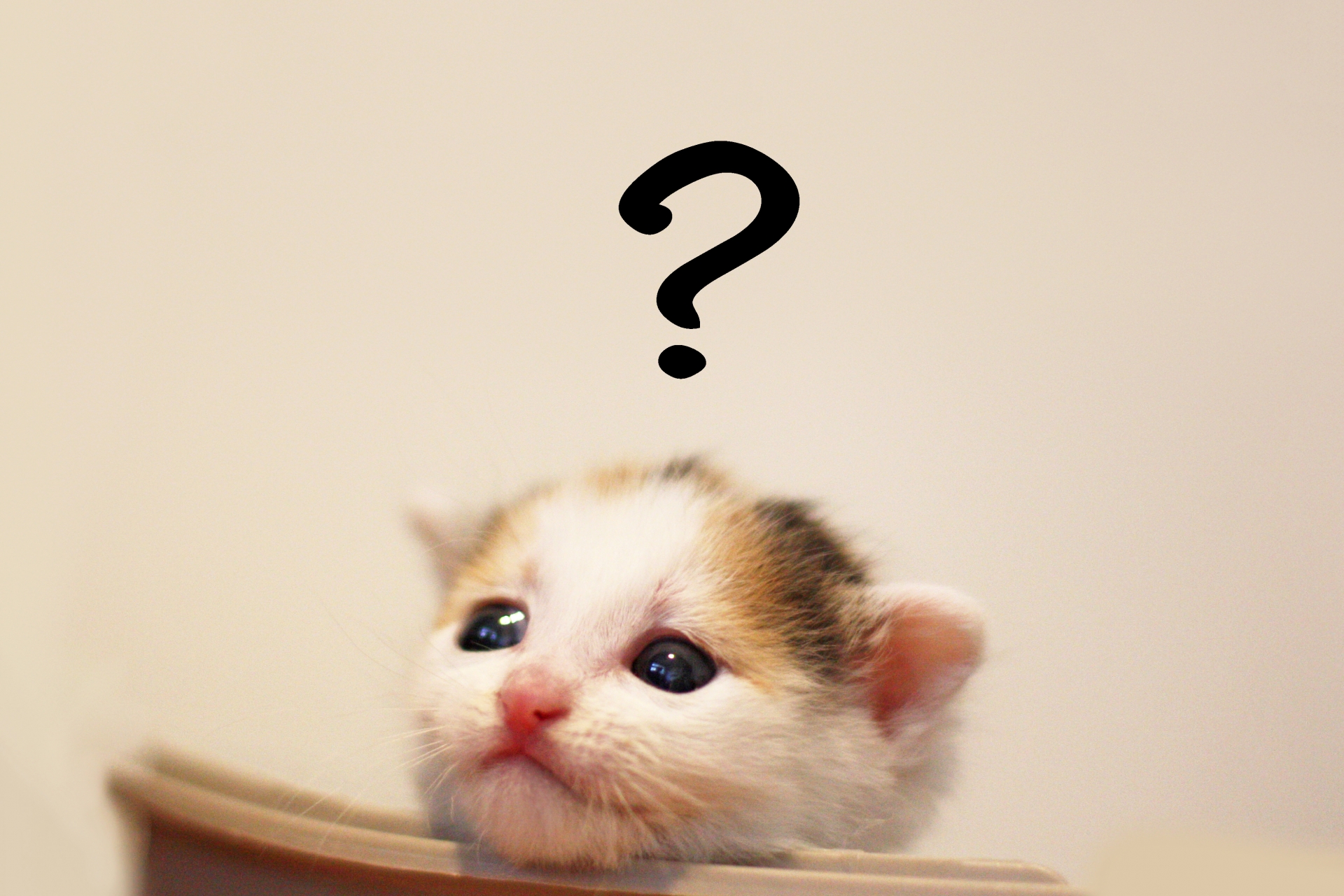






































コメントを残す